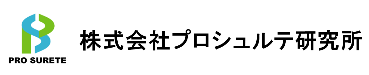製品安全について
製品安全について
製品安全は、”暗黙の品質”とも言われます。
安全は品質の一部ですが、普段は声高な主張をしません。ところが、製品事故が発生すれば、様相は一変し、品質の最も重要な位置を占めるのです。
消費者が製品を購入する際に、まず検討することは、
・ 機能
・ デザイン
・ 価格 ではないでしょうか。
中には、「安全を優先」して選択する方もいらっしゃるかもしれませんが、極めて稀と言えるでしょう。
消費者は、安全は「当然守られるべき権利」として、暗黙の合意とみなし製品を購入しているのです。
製造事業者、輸入事業者、販売事業者、龍津事業者及び保守事業者にいたるまで、製品安全を確保することは最も重要な責務であり、一貫した姿勢と行動が求められます。
原子力潜水艦の父、リコーバー提督はスリーマイルアイランドの原子炉事故から学ぶ組織運営上の教訓について証言するように招請された際に、示唆に富んだ、
【原子炉の安全運用7つの原則】を述べています。
ジェームズ・R・チャイルズ著 高橋健次氏訳 草思社
「最悪の事故が起こるまで人は何をしていたのか」より
(1) 時間が経過するにつれ品質管理基準をあげる。 許認可を受けるために必要な水準よりもずっと高くもっていく。
(2) システムを運用する人々は、様々な状況の下でその機材を運用した経験者による訓練を受けて、きわめて高い能力を身につけてなければならない。
(3) 現場にいる監督者は、悪い知らせがとどいたときでも真正面からそれを受け止めるべきであり、問題を上層部にあげて、必要な尽力と能力を十分につぎ込んでもらえるようでなければならない。
(4) この作業に従事する人々は、放射能の危険を重く受け取けとめる必要がある。
(5) きびしい訓練を定期的に行うべきである。
(6) 修理、品質管理、安全対策、技術支援といった機能のすべてがひとつにまとまってなければならない。その手立てのひとつは、幹部職員が現場に足を運ぶことだ。ことに夜間の時間帯や保守点検のためにシステムが休止しているとき、あるいは現場が模様替えしているときに。
(7) こうした組織は、過去の過ちから学ぼうとする意志と能力をもってなければならない。
この7つの原則は、原子炉の安全に関するものですが、一般の製品安全に対してもそのまま当てはまることではないでしょうか。
このカテゴリーの中で、製品安全に関する考察を述べていきます。
製品安全への考察記事一覧
企業が抱える製品安全上の課題
日本の製造事業を取り巻く環境の変化日本の製造事業を取り巻く環境は、かつての高度成長期から大きな転換期にあります。製品安全の視点からすれば、リスクのより高い環境下で日々の活動をやられているのが現状ではないでしょうか。新聞等マスコミで話題となったキーワードをピックアップしてみました。1) 日本の製造事業...
製品安全マネジメントシステム
プロシュルテ研究所が提唱する、製品安全マネジメントシステム(PSMS)について PSMS ; Product Safety Management System 企業が確保すべき製品安全は、次の3項目があります。<製品安全の実現>法令や強制規格に適合する合格点レベル...